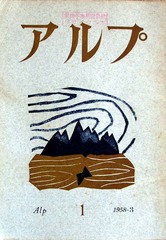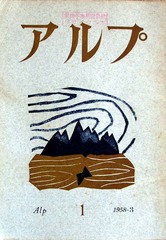
「北のアルプ美術館」
世古佳彦
山に関係する雑誌で「アルプ」というのがあったのを、大宮労山の今のメンバーで何人が知っているだろうか。「岳人」や「山と渓谷」のような山の総合雑誌ではなく、山の文芸誌と言った方がよいかもしれない。1958年に創刊された。そのとき職場の山の先輩から「世古君、今度こういう雑誌が出たのを知っているかい」と現物を見せてくれた。それはまったく斬新な編集であった。しかし登っている山のレベルも、文章のレベルも私には手の及ばない感じがしてとうとう一号も購入することがなかった。その後、仕事が忙しくなり、特に労働組合への分裂攻撃以後、山登りどころではなかった。
50歳を過ぎて登山を再開してからは山に関わる書籍はずいぶん読んだ。その中には「アルプ」に掲載されたものも少なからずあった。それによって「アルプ」という雑誌がすごくレベルが高かったことを知った。でもそのときには「アルプ」はすでに終刊にされてしまっていた。25年間に300号を発刊してそれを区切りに1983年に意識的に終刊にしたのだ。
編集委員には串田孫一(登山家、哲学者、東京外国語大教授)、尾崎喜八(登山家、詩人)、山口耀久(登山家)、三宅修(山岳写真家)、畦地梅太郎(版画家)、大谷一良(版画家)など錚々たるメンバーであった。
この終刊を惜しむ声は多かった。その中で「アルプ」に発表された作品の生原稿や関連資料を集めて保存、展示しようと考えた篤志家がいた。北海道斜里町の山崎猛氏である。上京して串田氏を訪ね、趣旨を説明し資料収集を要請した。串田氏は山崎氏が本気であることを確かめ、資料を段ボールに詰めて送り始めた。こうして「アルプ」が終刊して6年後に施設が完成した。
前々からこの美術館を訪ねたいと考えていたが今年6月やっと実現した。
「北のアルプ美術館」はJR斜里駅から徒歩20分のところにあった。白樺や七竈が植えられた1900坪という広い土地に建てられていた。もと三井農林の社員寮として使われていたその建物は木造二階建てで、暖房用の四角い煙突が三本並んでいて、一見して「アルプ」美術館にふさわしい建物であると感じた。展示品が多い割に場所がせまいので展示物が密集して並べられ、やや息苦しい感じがした。推測するに収蔵品はまだまだあるのだろう。そういうものも展示してほしい。あまり大きな建物はこの美術館の性格とは似合わないかもしれないが、何とか工夫がほしいと思った。来年には串田氏の書斎がそっくり移されてくるとのこと、ますます手狭になるだろう。
このとき鑑賞者は私たち夫婦二人だけで、入場料無料のうえコーヒーまでごちそうになりゆっくり楽しめ充実した気分で外に出た。 (〒099ー41 斜里町朝日町11−2 電話01522―4000)